犬をケージに入れると吠えたり、いったん鳴きやんでもまた吠えたりすることもあり、どのように対処したら良いか分からないという方も多いと思います。
自己流だと「これで良いのかな?」と心配になりますが、専門家からケージに慣れる方法を聞けると安心ですよね。
ここでは、ブリーダーさんから教えていただいた方法を参考に「ワンちゃんがケージ(ハウス)で吠えずに過ごしやすくなる方法」についてご紹介したいと思います。
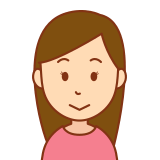
15年以上の実績があるブリーダーさんから教えていただいた方法をまとめています。
実践して効果的だった方法もご紹介しているのでぜひ参考にしてみてくださいね。
犬が自分からケージに入る理由
犬がケージから出てこない、ケージの中でずっと寝ている、といった状況はよくあることですが戸惑う方も多いようです。
犬が自分からケージに入るのはなぜ?もしかして具合が悪いのかな、と疑問に感じる方も多いようですが、犬は元々穴ぐらに寝床を作って過ごす動物。
元気なワンちゃんがケージで落ち着いて過ごしているときは、ケージが穴ぐらの代わりとなり落ち着く場所になっているようです。
犬が自分からケージに入って寝ている、ケージに入ったまま出てこない、という状況はワンちゃんがケージの中を落ち着く場所と認識しているからなので、悪いことではないということなんですね。
万が一災害などで避難所に行く際はクレートやケージの中で過ごすことが多くなるので、ケージを落ち着く場所にできると緊急時に備えられるといったメリットもあります。
大切なのは「ケージは楽しいところ」と認識すること
ケージに入った後吠えずに過ごすために大切なポイントは「ケージは楽しいところ」だと思えることです。
犬がケージに入って吠える大きな理由は「ケージの中が落ち着かない」「楽しくないところ」と思ってしまうことがあります。
ケージに入ると良いことがある、楽しいことがあると思うと自分からケージに入るようになります。
ケージに入った後に吠える場合は、ケージに入った後、静かにできているときにおやつをあげます。
こうすることで居心地の良い場所と認識するようになり少しずつ静かに過ごせるようになります。
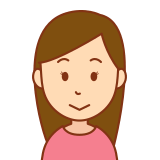
落ち着いて過ごすためにまずはケージの中が楽しい場所、落ち着く場所と認識することが大切なんですね。
初めはなかなかうまくいかないことも多いですがじっくり時間をかけて続けてみましょう。
思うようにいかないこともあります
とはいえ、なかなか思うようにいかないこともよくあります。
うまくいかないときも根気強くトレーニングを続けていくことで少しずつ認識が変わっていきます。
次にご紹介する方法で自身もワンちゃんが1歳になるころようやくケージの中で静かに過ごせるようにトレーニングできました。
「ケージに入れると吠えて静かにしない」「お留守番中も動き回ってケージの中がめちゃくちゃ・・・」という方もぜひ参考にしてみてくださいね。
ケージで落ち着いて過ごすためのトレーニング
ケージに入った後も落ち着いて過ごすためにまず行うトレーニングが「おやつ(ご褒美)で楽しいイメージを作る」という方法です。
ケージに入るときにおやつを1つ与え、静かにしていたらおやつを1つ与えます。
こうしてケージの中にいると良いことがあると認識させ、少しずつ落ち着いて過ごせるようにしていきます。
- Step1ケージに入るときに「ハウス」と言っておやつ・フードを見せる。
- Step2入ったらドアを閉める。
- Step3おやつ・フードを1つ与える。
- Step4静かにしていたらおやつ・フードを1つ与える。
静かにしているときはいつでもOK。吠えたり動いているときはお座り、伏せなど静かにさせてから与える。
- Step5お出かけの前におやつ・フードを1つ与える。
「おりこうにするんだよ」「マテだよ」など分かりやすいコマンドを伝えながら与える。
ケージに入るときに「ハウス」と言って、ちゃんと入れたらドッグフード、好きなおやつを1つでも良いので、手でご褒美を与えます。
このようにしてケージに入る→良いことがあると認識させていきます。
●ワンポイント●
犬は人が手に持っているものは何でも「良いもの」と認識する習性があるので、手で直接与えることでよりご褒美感を感じることができます。
ケージに入ったらおやつを1つ与えることを続けると、ごはんやおやつのときに自分からゲージの中に入って待つようになりました。
*おすすめのおやつ*
トレーニングのときに与えるおやつはボーロやキューブ型のものなど、1つずつこまめに与えられるものがおすすめです。



うまみの強いささみやビーフなどのおやつだとワンちゃんもとても喜んでくれます。
アレルギーが出たり噛む力が弱いワンちゃんはボーロなどの食べやすいおやつがいいですね。
実際に↑の絹紗を与えていますが、お留守番ができるようになったときにたまたま与えていたのが絹紗でした。
それからお留守番の前には絹紗を与え「おりこうにしとくんだよ」と言い聞かせて出かけています。
おやつが嬉しいようで静かに待ってくれることが多くなりました。
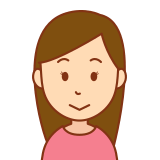
続けていくとおやつのときに自分からゲージやハウスに入っていくようになります。
初めはなかなかできなくても根気強く続けてみましょう。
ケージに入る→良いことがある(おやつがもらえる)
このアクションができるようになると、ケージに入った後ご褒美をもらってワンちゃんが満足し、無駄吠えをしなくなるという流れを作ることができます。
無駄吠えをしている間は相手にせず、どうしても吠え続ける場合は静かにするよう一声かけます。
吠えても誰も相手をしてくれないと理解するまで少し時間がかかるかもしれませんが、根気よく続けていくとケージの中で落ち着いて過ごせるようになります。
ケージの中で過ごせるようになるとクレート(キャリーケース)の中で過ごすこともできるようになります。
排せつのリズムができあがる生後7か月ごろからクレートの中で5~6時間程度のお留守番をさせることもできるようになるので、ケージの中で落ち着いて過ごすトレーニングをしておくとお留守番もしやすくなります。
ケージに慣れるための基本
犬がケージに慣れるために知っておきたい日常生活での基本ルールが3つあります。
- ケージに入るとき手でご褒美を渡す。
- おりこうにできたらご褒美をあげる。
- 寝るとき、お留守番はケージで過ごす。
このルールを基本に過ごすことでメリハリのあるしつけを行うことができ、犬も人も一緒に過ごしやすくなります。
➀ケージに入るときは手でご褒美を渡す
「ハウス」と言ってきちんとケージに入れた時は手でご褒美を与えて「良いことがある」と覚えさせていきます。
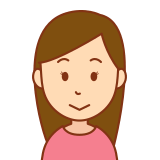
人間が手に持っているものにワンちゃんは何でも興味しんしん!
直接おやつをもらえると嬉しさもより大きくなるんですね。
ご褒美はおやつやフードを1つ与えるだけでOKです。
静かにしているときはおやつを何度かあげても良いので「静かにしていると良いことがある」と理解していくようにトレーニングしていきます。
➁おりこうにしているときはご褒美
ケージに入った後もおりこうに過ごしているときはご褒美をあげると、おりこうに過ごす→ご褒美がもらえると認識し静かに過ごすことが増えていきます。
ご褒美はトレーニングを行う上ではとても効果的な方法なので、できた→ご褒美がもらえるという習慣をつけていくとトレーニングを進めやすくなります。
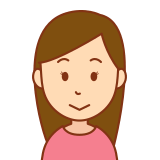
お留守番前後、ケージの中で上手に過ごせたときにご褒美におやつを1つ与えるを繰り返すことで静かにする→ご褒美とワンちゃんも覚えやすくなります。
③寝るとき、お留守番などケージで過ごす時間を作る
寝るとき、お留守番のとき、お部屋で一緒に過ごすことができないときなど、そばで見てあげられないときはケージで過ごすようにします。
この習慣を続けていくことで吠えたり、要求吠えで吠え続けたりすることが少なくなっていきます。
寝るとき、お留守番のとき自由にさせるとまた始めからやり直し。
日によって一緒に寝たり、お留守番をお部屋で自由にさせてしまうとケージに入れたときに吠えたり要求吠えを始めてしまいます。基本的に寝るとき、お留守番はケージで過ごす習慣をつけましょう。
静かにできていたのにまた戻ってしまったら・・・
ケージで静かに過ごせるようになっていたのに吠えることが多くなったということも時々あります。
そんなときは先ほどご紹介した「ケージに入る→おやつを与える→静かにしていたらおやつ」を繰り返すことで静かに過ごせるようにしていきます。
焦らずにできたらご褒美を実践しながら進めていきましょう。
要求吠えの主な理由
ケージに入れたとき吠え続ける「要求吠え」には主にこのような理由があります。
出してほしいとき
ケージに入れられたことでもっと遊びたい、出して自由にしてほしい、などの要求で吠えることがあります。
寝るとき、お留守番をケージでしていたのに、寝るときにケージから出したままにしていたり、お留守番を自由にさせてしまったあとにケージに入れると吠えることもあります。
こうなるとまた初めからやり直しになるのでケージで過ごす習慣を決めたら慣れるまでしっかり守るようにしましょう。
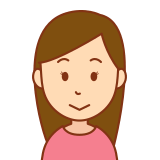
吠えても出してもらえないと理解できるまで途中でやめずに根気強く続けていくことがポイントですね。
排泄物を片付けてほしいとき
トイレが汚れたり足の裏に排泄物がついてしまい、きれいにしてほしい時に吠えて教えてくることもあります。
夜中に吠えるときは静かに犬の様子を見に行き、排せつ物でトイレや足裏が汚れている場合はきれいに片づけてあげましょう。
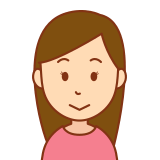
清潔できれいな場所で過ごしたいのはワンちゃんも同じです。
ケージの中や身体が排せつ物で汚れている場合はきれいにして気持ちよく寝られるようにしましょう。
寂しいとき
一人になるのが寂しくて吠えることもよくあります。
遊んでほしいときと似ていますが、ケージに入ってお部屋から人がいなくなるのが寂しいという理由から吠えてしまうこともあるんですね。
このとき、一緒に過ごしてあげるという方法もありますが吠える=一緒にいてくれると認識してしまうこともあるのであまりおすすめはできません。
寂しい気持ちをできるだけ感じさせないように工夫すると吠えなくなることもあります。
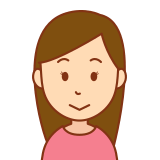
ワンちゃんも寂しくて誰かに一緒にいてほしいと感じることもあるんですね。そんなときは寂しさを紛らわせるおもちゃやクッションなどを一緒に入れてあげると落ち着くことも。
対処法については後ほど詳しくご紹介しているのでぜひ参考にしてみてくださいね。
要求吠えの対処法
要求吠えをするときは理由に合わせてこのような対処法があります。
出してほしくて吠える場合
ケージの中も汚れていなくて出してほしくて吠えている場合は、相手をせずに静かになるまでそのままにしておきます。
誰も相手にしてくれないと分かると諦めて眠るので、諦めて眠るまで相手にせずそのまま様子をみましょう。
どうしても静かにならない場合は・・・
夜中で近所迷惑になってしまうかも、という場合は、1度、2度ほど「静かにしなさい」と叱ると諦めて静かに眠ることもあります。
どうしても静かにならない場合に考えられること
どうしても静かにならない場合はその日どのように過ごしたかを思い返してみると何か思い当たることがあるかもしれません。
1日のうちケージから出してもらえる時間が極端に短い場合はストレスで吠え続けることもあります。
ストレスで吠える場合は、少し出してストレスを発散させると落ち着くこともあるので、お留守番が長くなった日などは自由な時間を作るなどストレスにならないように気を付けてあげましょう。
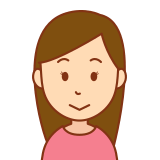
ゲージに入っている時間が長いときは自由な時間を作ってストレス発散すると要求吠えがなくなることもあります。ケージで過ごす時間と自由な時間のバランスにも気を付けたいですね。
排泄物(うんち)を踏んだ場合
排泄物をきれいにしてほしくて吠える場合は、ケージの中と足裏をきれいにしてすぐに寝かせます。
手順としてはこのようになります。
- Step1消臭剤で足裏のうんちをふき取り、お部屋に放す。
このとき遊んだり構ったりせず、静かに体についた排せつ物をきれいにします。
- Step2ふき取れない場合は洗面所やお風呂場で洗い流してからお部屋に放す。
爪の間や足裏などにべったりついている場合はぬるま湯でやさしくきれいにしてあげます。
- Step3お掃除をしたらワンちゃんをケージに戻し、すぐに離れる。
ワンちゃんは得か損かで判断する面があるため、このときにすぐ離れることでケージを汚しても誰も遊んでくれない(良いことがない)ことを理解していきます。
足裏をきれいにしてからお掃除の間はお部屋で自由に遊ばせても構いません。
このとき、遊んだり構ったりせずにお掃除に専念して、片付けが終わったらケージに入れてすぐにその場を離れます。
このとき遊んだり構ってしまうと「吠えたら遊んでくれる」「うんちを踏んだら遊んでくれる」と認識してしまうこともあるのでここでは静かに片づけに専念します。
片付けが終わったら再びケージに入れ、「おやすみなさい」と一言声をかける程度にし、すぐにその場を離れます。
要求吠えは無駄に吠えていると思われがちですが、きちんと理由があって吠えていることもあるので、その時の状況に応じて対処することで要求吠えを減らすことができます。
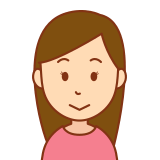
排せつ物の掃除の後ケージに入れるときにおやつを与えてもOKです。ケージに入る=いいことがあると理解すると要求吠えもなくなり、静かに休むようになります。
このようにケージに入った後満足感を感じることで落ち着いて過ごせるようになることもあるのでぜひ参考にしてみてください。
寂しくて吠える場合
ワンちゃんの中にはパパ犬・ママ犬がおとなしい性格なのにお留守番や就寝時にいつも吠えている、離れるとケージ内でペットシーツがくちゃくちゃになるほど動き続けている、ということもあります。
ワンちゃんの性格によってはケージで一人になると寂しさのあまりペットシーツを噛んだり、吠えたりしてはいけないと分かっていても寂しさを紛らわすためにやってしまうことも。
寂しい気持ちが原因の場合は、このような対処法が効果をあげることもあります。
- 大きめのクッションやぬいぐるみを一緒にケージに入れてみる。
- コートを着る、マスクをつける、バッグを持つなど出かける前のルーティーンを見られないようにする。
- 玄関のカギを時々さわって音に慣れさせる。
- 運動したり遊んだりして体力・精神面で満足感を得られるようにする。
- 長く遊べるおもちゃを一緒に入れてみる。
大きめのクッションやぬいぐるみを一緒に入れてみる。
ふわふわとやわらかい感触はワンちゃんも大好きなので、大きめのクッションなどの上で気持ちよく温かい感触を感じると安心して落ち着くこともあります。
ケージで一緒に過ごすアイテム例
出かける前のルーティーンを見せない。
コートを着る、マスクをつける、鍵やバッグを手に持つなど、出かける前に何気なく行うしぐさがワンちゃんにとっては「一人になる」というサインになり吠えたりケージの中でいたずらをしてしまうことも。
出かける準備は別の部屋で行ったり、普段からお部屋でコートを着る、鍵を手に持つといった行動を見せることで慣れていき静かに過ごせるようになっていくこともあります。
玄関の鍵やドアの音に慣れさせる。
玄関を出たら早速吠えている・・・という経験をされた方は多いと思いますが、ワンちゃんにとっては一番分かりやすく寂しさを感じやすいポイントでもあります。
普段から玄関の鍵やドアの音を聞かせて「音がしても寂しくないよ」ということを感じることで吠えることが少しずつ減っていくことがあります。
運動したり遊んだりして体力・精神面で満足感を感じられるようにする。
お散歩に行ったりおもちゃで遊んだりして体力を使うことでケージの中で落ち着いて過ごせるようになることもあります。
お散歩や遊びの時間はワンちゃんにとっても嬉しい時間なので、満足感を感じることで気持ちが落ち着きケージで静かに過ごせるといった面もあるようです。
一緒に遊ぶアイテム例
長く遊べるおもちゃを一緒に入れてみる。
牛の蹄(ひづめ)のような犬が好んで長く遊べるおもちゃを入れて「ケージは楽しいところ」と認識させるのも1つの方法です。
牛のひづめはペットショップでも子犬が過ごすスペースに置いて遊ばせていることも多いため、安心して遊ばせることができます。
長く遊べるおもちゃアイテム例
※長時間遊べるおもちゃ(おやつ)としてよく購入されるアイテムですが、与える際はワンちゃんの様子を見ながら安全に気を付けて与えるようにしてください。
かまってほしい、一人にしないでほしい、という気持ちをうまく落ち着かせることでケージの中でも安心感をもって過ごせるようになることもあるんですね。
ケージの中でも安心して過ごせるようにぜひ参考にしてみてください。
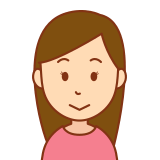
どの方法も即効性があるというわけではありませんが、少しずつ慣れさせていくことがポイントです。初めはうまくいかないこともありますがワンちゃんのペースを見守りながら根気強く続けてみてくださいね。
どのくらいで落ち着いて過ごせるようになる?
ケージで静かに眠れるようになる期間はワンちゃんの性格や個体差があるため、明確に何か月ごろといっためやすはありませんが、成犬になるまでの1年間は根気強く続けていくことがポイントです。
成犬期を迎えたときに習慣づけができているとワンちゃんにとってもご主人にとっても過ごしやすい環境を作ることができます。
また、成犬期を過ぎても新たにしつけを始める場合は最低でも半年はかけて慣れされることがポイントです。
すぐにできないからと諦めるのではなく、じっくりと時間をかけて少しずつ慣れさせていきましょう。
しつけ教室や獣医師など専門家の力を借りる
どうしてもうまくいかない場合は専門家に相談することも1つの方法です。
しつけ教室に通ったり、獣医師に相談するといったことを検討されてみても良いと思います。
子犬期のしつけについて獣医師に相談できる獣医師監修【こいぬすてっぷ】といったサービスを利用するのも1つの方法です。
後ほどご紹介しているので興味のある方はぜひ参考にしてみてください。
初めはうまくいかず悩むことも多いですが、基本的にはワンちゃんと楽しい時間をたくさん過ごすことが信頼関係を築いていくポイントです。
根気強く、ときには専門家のアドバイスも取り入れて焦らず続けてみましょう。
獣医師監修の子犬期のしつけキットを活用する
ここまで自身がブリーダーさんから聞いた内容をもとに「ケージに慣れる方法」についてご紹介してきましたが、
- 専門家から直接教えてもらいたい。
- 専門家にしつけ相談がしたい。
という方は獣医師監修【こいぬすてっぷ】といったサービスを活用するのもおすすめです。
こいぬすてっぷとは?
こいぬすてっぷは獣医師監修のしつけキットで犬種や月齢に合わせた育て方本と日用品やおもちゃが届くサービスです。
獣医師が完全監修でしつけ相談、アレルギーにも対応しているので子犬を育てるのが初めての方も安心して利用できます。
こいぬすてっぷは毎月ワンちゃんに合わせたしつけキットが届くサービスですが、お試し1回のみの利用もできます。
こいぬすてっぷの詳細、1回お試しキットについてはこいぬすてっぷ公式サイトにてご覧ください。
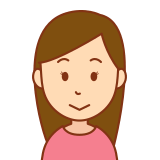
こいぬすてっぷは2か月~1歳のワンちゃんにおすすめです。1歳になるまでが大切な時期といわれています。この時期にしつけに関する情報や相談ができるのはとても助かりますね。ぜひ参考にしてみてください。
まとめ
子犬期は成犬期を分ける大切な時期なのできちんとしつけをしたいという方も多いと思います。
犬をケージに入れるときの大切なポイントはケージに入れるときにご褒美を与えて「良いことがある」と覚えさせるということになります。
また、ケージで過ごす時間と一緒に過ごす時間をきちんと分けることでメリハリのあるしつけができ犬も人も一緒に過ごしやすくなります。
慣れるまでは寝るとき、お留守番のときなどお部屋で一緒に過ごす以外はケージに入れることを徹底するくらいの感じでいっても良いでしょう。
ケージに入ることは楽しいこと、そしてケージで過ごすことに慣れると少しずつ吠えることが少なくなっていくので根気強く教えていきたいですね。
犬をケージに入れると吠えたり、要求吠えで吠え続けたり、何とかしたいけど方法が分からない、自己流で良いのか迷っている方の参考になればと思います。
参考文献:ミニチュアダックスフンド 飼い方・しつけ・お手入れ
「ミニチュアダックスフンド 飼い方・しつけ・お手入れ」はワンちゃんとの接し方、しつけのポイントを分かりやすく解説されています。
どうしてこの方法が効果的なのか?ワンちゃんの習性をもとに「なるほど」と納得しながら参考にさせていただきました。
ミニチュアダックスだけでなく他犬種にも参考になると思うので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
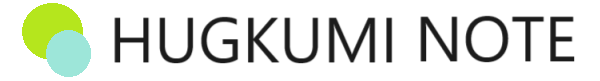








時々お留守番中に吠えたり、ケージの中を荒らしてしまうこともありますが・・・
ワンちゃんも状況によって寂しかったり、気分もいろいろだと思うのでうまくできないこともあります。
ですが、前よりも静かに過ごしていることが増え、お留守番させやすくなりました。