やよいの白色申告オンラインはすべての基本メニューが無料で使えるので確定申告で白色申告を行う方におすすめです。
在宅ワークで空いた時間に仕事をして収入を得たい、収入を得ても扶養の範囲で仕事をしたい方は多いと思います。
在宅ワークと一言に言っても職種や仕事内容はさまざまで、複数の在宅ワークを行っている方の中には気づいたら扶養の範囲を超えていた、ということもあるので注意が必要です。
扶養の範囲内で仕事を続けるためには、気を付けたいポイントがいくつかあります。
ここでは、在宅ワークで扶養の範囲内で仕事を続けるときに気を付けたいポイント、さらに扶養内でも確定申告が必要なケースについて実体験を含めて見ていきたいと思います。

在宅ワークを始めたきっかけ
在宅ワークを始めて約4年ほどになりますが、始めたきっかけはクラウドソーシングサービスで在宅で仕事を始められることを知ったことがきっかけでした。
子どももまだ2歳くらいで小さく、外で働くよりも在宅で家にいながら仕事ができたら良いな、と思いクラウドソーシングサービスでお仕事を探し、ライティングの仕事を見つけたことがきっかけでした。
扶養の範囲内で仕事をするということは?
扶養は2つのポイントに分かれ、社会保険上の扶養と税制面の扶養があります。
- 社会保険=社会保険を支払っている扶養者(夫もしくは妻)の健康保険・年金保険に扶養で入る。
- 税制面=夫もしくは妻が扶養に入ることで社会保険料を支払っている配偶者が配偶者控除を受けられる。
といった2つのポイントがあります。
扶養の範囲内で働くと社会保険に扶養で入ることができ、夫もしくは妻が扶養に入ることで配偶者が配偶者控除を受けられます。
扶養の範囲内で仕事をする主な理由
扶養には社会保険上の扶養と、税制面での扶養の2つがありますが、扶養の範囲で働きたい理由についてはこのような理由があります。
- 社会保険の扶養から抜けずに仕事をしたい。
- 長く続けられるか、安定して収入を得られるか気になる。
- 扶養者が扶養控除(配偶者控除)を受けられる範囲で仕事をしたい。
社会保険の扶養の条件として年間の収入額が130万円以下(※3)であることと定められているため、年収が130万円を超えると扶養から外れることになります。
※3 企業によっては106万円以下
扶養の範囲を超えてしまうと扶養から外れ自身で社会保険料(健康保険料・年金保険料)を支払う義務が発生します。
扶養の範囲内であれば自身で社会保険料を支払う義務は発生しないことと、健康保険は「被扶養者」として、年金保険は「国民年金第3号被保険者」として社会保険を受けることができます。
また、税制面でも扶養の範囲内で仕事をしていると配偶者が扶養控除(配偶者控除)を受けられるといったこともあり、扶養の範囲内に収めたいという方も多いようです。
税金面では被扶養者の年収が103万円を超えると配偶者控除が受けられなくなります。
そのため、社会保険の扶養と税制面の控除を最大限受けられる範囲(年収103万円以下)、もしくは社会保険の扶養の範囲内(年収130万円以下※3)で仕事をしたいという方が多いようです。
※3 企業によっては106万円以下
こういった理由から、扶養の範囲内で在宅ワークを続けたいという方が多いようです。
扶養の範囲内で仕事をするときに気を付けたいポイント
扶養の範囲内で働く場合に気を付けたいポイントには、
- すべての収入を合算して扶養の範囲内を超えないようにする。
- 年間の収入額か、1か月の収入額で判断するか確認する。
- 社会保険の支払いが発生しない範囲(年収130万円以内※1)に収まっているか確認する。
といったポイントがあります。
※1 企業によっては年間130万円以内ではなく、年間104万円以上の収入から社会保険加入義務となることもあるため、自身の勤務先、扶養者の勤務先に確認しておくと安心です。
また、在宅ワークで雇用されない形態(請負、フリーランスなどの個人事業主)でパート・アルバイトなどのように給与所得控除(※2)がない場合は、年収130万円以内ではなく年収48万円以下(年間所得48万円以下)に収める必要があります。
※2 給与所得控除=年収から年間55万円の控除を受けられる制度。
ですが、雇用されない形態で在宅ワークをする方も、給与所得控除と同額の控除を受け年収130万円以内の範囲で扶養内で仕事をすることが可能です。
こちらについては後ほど「扶養の範囲内で働く:在宅ワークとパート・アルバイトの違い」でご説明しているので参考にしてみてください。
複数の収入源がある場合は総額で扶養の範囲内かを確認する
在宅ワークを複数請け負っている場合はすべての収入を合算した総額が扶養の範囲内となるかの基準額となります。
在宅ワークで複数の収入源がある場合は、1つの仕事に対しての収入額ではなく、課税対象となる全ての収入の総額で扶養の範囲に収まるかどうかを見ることになります。
在宅ワークの主な収入源
在宅ワークの主な収入源にはこのような形態があります。
- ブログ運営、アフィリエイトで収入を得る。
- クラウドソーシングを利用して収入を得る。
- 商品を仕入れネット通販で販売する。
- ハンドメイド作品をネットで販売する。 など
上記のようにアフィリエイト収入、クラウドソーシングサービス、ハンドメイド作品の販売などで収入を得ている場合は全ての収入を合算して扶養の範囲かどうかを見ることになります。
自宅の不用品などを売った収入はどうなる?
ここで気になるのが不用品などを売った収入についてですが、不用品を売った収入は基本的に確定申告の対象にはならないとされています。(※)
※一時的な収入で営利目的でない場合
ですが、下記に該当する場合は確定申告の対象になる場合もあるので注意が必要です。
- 高額な売値で取り扱われる商品(宝石、骨董品など)を売った収入
- 不用品を継続的(定期的・頻繁に)売って収入を得ている場合
すべての基本メニューが無料で使えるので確定申告で白色申告を行う方におすすめです。
扶養から外れる基準は企業によってさまざま
扶養から外れる基準は一律で決まっているわけではなく、
- 「月収10万8334円を超えた月から」
- 「月収10万8334円を超えた月から続けて3ヶ月間超えた場合」
- 「年収が130万円を超えた段階から」
と、月収額が基準になる場合や年収ベースで見る場合など企業や加入している健康保険によって様々です。
扶養から外れる基準について確認したい場合は、企業や加入している健康保険に問い合わせてみましょう。
在宅ワークで扶養の範囲内で収入を得るためのポイント
在宅ワークで扶養の範囲内で収入を得るポイントにはこういったことがあります。
収入額を月10万円以下に抑える
扶養の範囲内で仕事を続ける場合、基本的なポイントとしては「年間130万円以下の収入に抑える」ということですが、年間130万円以下ということは基本的に月収10万8334円以下ということになります。
月10万円以上の仕事を行う場合は収入をしっかり管理する
在宅ワークの募集では「月10万円以上可」「すき間時間に高収入」といった案件もあり、在宅ワークのお仕事にはさまざまな職種、仕事内容の案件が多くあります。
より多くの収入を得られるということで「月10万円以上可」といった案件を選ぶ方も多いかと思いますが、扶養の範囲内で仕事を続ける場合は収入を扶養の範囲内(年間130万円以内※)に抑えることがポイントです。
※ 企業によっては年間130万円以内ではなく、年間104万円以上の収入から社会保険加入義務となることもあるため、自身の勤務先、扶養者の勤務先に確認しておくと安心です。
扶養の範囲内で住民税・所得税が非課税になる範囲
在宅ワークでもパート・アルバイト・会社員など正規雇用と同じように一定額を超えると所得税、住民税の支払い義務が発生します。
社会保険の扶養の範囲内で、さらに所得税、住民税が非課税の範囲で在宅ワークを行いたい場合は、年収98万円以下に収まる範囲で収入を得ることがポイントになります。
- 所得税・住民税(※4)の両方を非課税にしたい場合は「年収98万円以下」
- 所得税非課税、住民税の支払いあり・・・「年収103万円以下」
- 所得税・住民税の支払いあり・・・「年収130万円以下」
ただし、これはパート・アルバイト等で雇用される場合で、在宅ワークで請負(フリーランス)で仕事を受けている場合はあてはまりません。
請負(フリーランス)の場合は、雇用される場合に適用される給与所得控除(55万円の控除)がないので、このような形になります。
- 所得税・住民税(※4)の両方を非課税にしたい場合は「年収43万円以下」
- 所得税非課税、住民税の支払いあり・・・「年収43~48万円以下」
- 所得税・住民税の支払いあり・・・「年収48万円以上」
年収43万円を超えると住民税、48万円を超えると住民税と所得税の両方が発生することになります。
雇用されて働く方と請負(フリーランス)で働く方はこのような大きな違いがあります。
ですが、請負(フリーランス)で在宅ワークをしている方でも給与所得控除と同じ額(年間55万円)を控除できる優遇措置が適用されることがあります。
こちらの記事でご説明していますので参考にしてみてください。
※4 住民税については自治体によって収入の基準が異なる場合があるため、住民税の課税対象となる収入額については管轄の市役所・区役所の市民税課に確認しておきましょう。
すべての基本メニューが無料で使えるので確定申告で白色申告を行う方におすすめです。
扶養の範囲内で働く:在宅ワークとパート・アルバイトの違い
先ほどお話したように扶養の範囲内で働く場合、パート・アルバイトで働く場合と在宅ワークでは異なるポイントがあります。
それは所得税の算出方法です。
パート・アルバイトのように事業者に雇用されて働く場合、給与所得控除が適用され年間の収入総額から55万円を差し引いた額を所得額として所得税が算出されます。
そのため、年間収入が103万円でも控除額55万円を引くと所得額は48万円となり、所得税非課税の範囲(年間48万円以内)に入るため所得税はかからないということになります。
ですが、ここでぜひ知っておきたいのが在宅ワークでも経費として年間55万円の控除を受けられる家内労働者の特例という制度です。
在宅ワークでも年間55万円を差し引くことができる
家内労働者の特例を適用すると在宅ワークでもパート・アルバイトで働く方と同じように年間55万円を引いた金額を所得金額とする特例措置を受けることができます。
実際に自身も確定申告を行い家内労働者の特例の書類を添付して税務署へ提出し適用を受けています。
(ご参考までに:自身の年間の総収入額は90~100万円の範囲です。)
家内労働者の特例を適用した確定申告についてはこちらの記事でご紹介しているので、参考にしてみてください。
扶養の範囲内でも確定申告が必要なケース
確定申告を行う基本的なポイントとしては、在宅ワークでパートと同じように55万円の控除を受ける場合は確定申告が必要となります。
家内労働者の特例で所得税、住民税の優遇措置を受ける
先ほどお話した給与所得控除と同じように年間55万円の優遇措置を受けるためには基本的に確定申告を行う必要があります。
確定申告をしなくても適用の条件にあてはまるからしなくても良い、という考え方もありますが、税務署の判断によるので、基本的には確定申告をしておいた方が良いと思います。
(税務署の職員の方の判断もさまざまなようなので、確定申告をしておいた方が確実かもしれません。)
健康保険の扶養認定で確定申告の控えが必要な場合
在宅ワークで収入がある場合、年間43万円以下の収入でも非課税証明書(所得証明書)に収入額・所得額が明記されます。
収入が0円(無収入)場合は非課税証明書には0円と記載されるため、非課税証明書のみの提出で済みますが、収入がある場合は税務署の印鑑が押された確定申告書の控え(または準ずるその他の書類)の提出を求められることがあります。
被保険者(扶養者)に転勤・転職の予定がある場合は、確定申告をしておくと控えを求められた場合でもスムーズに手続きが進められます。
すべての基本メニューが無料で使えるので確定申告で白色申告を行う方におすすめです。
在宅ワークで確定申告を行うメリット
在宅ワークで扶養の範囲内でも確定申告を行っておくとこのようなメリットがあります。
- 所得額が所得税、住民税の優遇措置の範囲内に収めることで税金がかからなくなる(税額を抑えることができる)。
- 転勤・転職等で扶養認定や検認があったとき手続きをスムーズに行える。
メリット1:所得税、住民税の優遇措置を受けることができる
55万円の控除を受けることで雇用されているパート、アルバイトの方と同様に所得税・住民税の優遇を受けることができます。
こういったことから個人事業主で雇用されていない場合で、
- 年収48万円を超える場合
- 経費等を差し引いた所得額が48万円を超える場合
にあたる方は、確定申告を行うことで所得額が税金の優遇措置の範囲内に収まることもあるため、確定申告の検討をおすすめします。
住民税・所得税が発生する基準
住民税・所得税が発生する所得額の基準としては、
- 所得額が43万円を超えると住民税の支払い義務が発生する。
- 所得額が48万円(基礎控除額)を超えると所得税の課税対象になる。
といったポイントがあります。確定申告は税制面の優遇措置を受けられる、また収入面を管理することで扶養の範囲内で仕事を続けやすくなるといったメリットがあります。
後で未納の税金が発覚すると追徴課税のペナルティを受けることがあるので、もしかしたら住民税、所得税が発生するかも?と思ったら市役所の税務課・または管轄の税務署に相談してみましょう。
メリット2:転勤・転職で扶養認定や検認があったとき手続きを進めやすい
さらに、扶養の範囲内で在宅ワークを行う上で健康保険・年金といった社会保険の手続きは、被保険者(社会保険に加入している本人)の健康保険に被扶養者として加入することになります。
ここで必要になるのが被扶養者の「収入の証明」になります。
年間収入48万円以下でも確定申告の控えが収入の証明書類になる
非課税の場合、非課税証明書の提出だけで済む場合は問題ないですが、収入がある場合は非課税証明書(所得証明書)の他に、確定申告書の控えの提出も求められることもあります。
こういった場合でも確定申告をしておくと健康保険の切り替え時など扶養認定の確認書類として確定申告の控えを提出できるので、スムーズに手続きを進められるといったメリットがあります。
また、確定申告をしておくことは今後、確定申告が必要な収入額になったときも手続きしやすくなるのでそういった意味でも将来的にメリットがあるといえるでしょう。
収入がある場合の提出書類については加入する健康保険によって異なるので、必要な添付書類を確認して提出しましょう。
収入0円等で証明書が発行できない、確定申告していない場合
自治体によっては収入0円で証明書が発行できない(収入ありで確定申告していないので証明書が発行できない)という場合もあります。
自治体によってはこのように収入0円でも市役所の税務課で市・県民税申告書で所得の申告→非課税証明書(所得証明書)の発行となることもあるので少し余裕をもって手続きを行えると安心です。
ここで発行された非課税証明書(所得証明書)には収入額0円でも収入額、所得額が明記されるので確定申告書の控えがない場合はこちらの書類を提出するだけでOKということもあります。
確定申告をしていない方で収入の証明が必要な方は非課税証明書(所得証明書)で良いか提出先に確認してみましょう。
扶養認定で非課税証明書(所得証明書)の提出が必要な理由
健康保険の適正利用のため、被扶養者が扶養基準に該当するかを確認するため、また、被保険者と同居・別居の状況を公的な書類で確認するために提出することが求められています。
自治体によっては年間収入がない=0円の場合、非課税証明書(所得証明書)の発行ができない場合もあります。
発行ができない場合は、市民税・県民税の申告書で無収入であることを申告してから手続きを行うと発行してもらえることが多いです。
会計ソフトを使って確定申告に備える
確定申告というと何となく面倒そう、どうやって記入したら良いか分からない、などいろんな疑問が出てきますが、確定申告をスムーズに進めるためにオンライン会計ソフトを使っている方も多くいらっしゃいます。
オンライン会計ソフトやよいの白色申告オンラインでは、在宅ワーカー、個人事業主向けの帳簿作成、確定申告をサポート。基本メニューを無料で利用できるフリープラン、質問やサポートが受けられる有料プランと目的に合わせてプランを選べます。
プランについては公式サイト内の下部に分かりやすく紹介されているので、会計ソフトに興味のある方はぜひチェックしてみてくださいね。
公式サイト:やよいの白色申告オンライン
弥生会計の確定申告ソフトの詳細、プランについてはこちらからもご覧いただけます。
→個人事業主向けのクラウド確定申告ソフトはこちら
扶養の範囲を超えてしまったときに気を付けること
ここまで扶養の範囲を超えないために気を付けたいことについて見てきましたが、扶養の範囲を超えてしまったときに気を付けたいことにはどんなことがあるでしょうか。
年間の収入額が130万円(月収10万8334円)を気づいたら超えていた場合、気づいた段階で扶養対象から外れている可能性があるため、できるだけ早めに確認の手続きを行いましょう。
そのまま放置しているとペナルティの対象に
扶養から外れている状態でそのまま放置していると、会社の家族手当などの福利厚生を受けられなくなる、さらには会社が虚偽の年末調整を行ったということで会社がペナルティを受けることもあるので注意が必要です。
また、税金面で扶養控除を適用している場合、追徴課税のペナルティを受けることもあるため、予定外の支払いが発生することもあります。
自身の収入額がどのくらいあるか?確定申告の必要性を管理するといった面でも先ほどご紹介したオンライン会計ソフトを活用するのも1つの方法ですね。
弥生会計の確定申告ソフトについてはこちらからご覧いただけます。
→個人事業主向けのクラウド確定申告ソフトはこちら
まとめ
在宅ワークで扶養の範囲内で仕事を続けるために気を付けたいことについて見てきましたが、ポイントは「月額10万円以上の収入に気を付ける」「複数の収入がある場合は合算して月々の収入を割り出す」「確定申告をして健康保険などの扶養認定に備える」といった大きく3つのポイントをご紹介しました。
確定申告については収入額によっては必要ないこともありますが、扶養認定に備える他に税金面について知ることもできるので確定申告をしておくとメリットもあるでしょう。
特に気を付けたいのは気づかずに月収10万8334円を超えていた、ということで、この場合、扶養を抜ける手続きを行わないと被保険者・働いている会社にもペナルティが課されることがあるため注意が必要です。
在宅ワークは働く形としてメリットの多い働き方なので、扶養の範囲内で仕事をしたい方は気を付けたいポイントを参考に扶養の範囲で長くお仕事を続けられると良いですね。
ぜひ、参考にしていただけたらと思います。
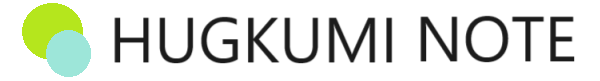




おすすめポイントは「誰でも使いやすい画面」と「会計士・税理士推奨」でオンライン会計ソフト利用者の2人に1人が利用しているという評判の高さ。
やよいのオンラインソフトは商工会議所の帳簿付け講座でも利用されています。
有料プランではチャットや電話・メールで相談もでき、初めての方でも安心して始められる会計ソフトです。確定申告を検討される方はまず無料で利用できるフリープランがおすすめです。